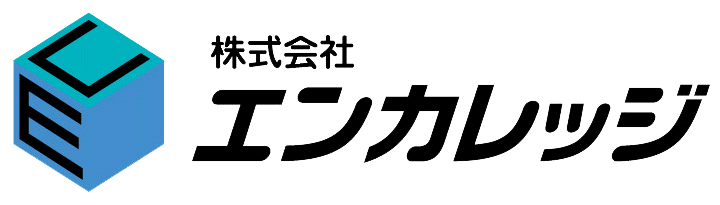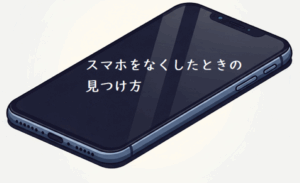間違えやすい日本語
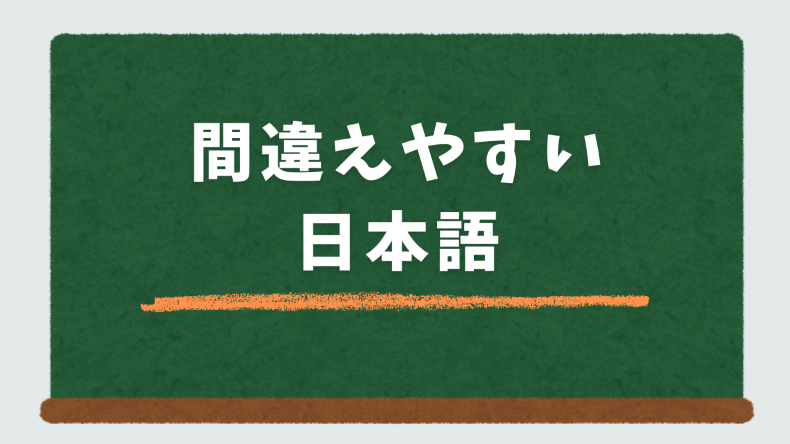
こんにちは。
日々の業務を行う中で、ふと、「この言い方って正しいんだっけ?」と思うことがあります。
メールの文章を書くとき、人と話すときなど。いつも気を付けてはいますが、間違った表現をしてしまうこともよくあります。皆様もそういった経験があるのではないでしょうか。
今回は、そんな間違えやすい日本語表現についてお話しできればと思います。
■ら抜き言葉
よく「誤った日本語表現」として挙げられる、代表的なものですね。
「見れる」や「出れる」といった言葉は、「見られる」「出られる」が文法的に正しい表現とされています。基本的には上・下一段活用の動詞や「来る」に助動詞「られる」が付いた形です。少々軽い印象を持たれてしまうケースもあるので、特にフォーマルな場では気を付けたい表現です。
■読み間違い
読み間違いも、気を付けたいポイントの一つです。
代表的なものが「雰囲気」でしょうか。「ふんいき」が正しい読みですが、つい「ふいんき」と呼んでしまいます。漢字の音読みを1つずつ見れば、「ふん+い+き」なのでわかりやすいですが、なんとなく語感で「ふいんき」と読んでしまいます。
また、IT業界でよく見かける「脆弱性」や「凡例」なども、間違えやすい熟語として知られていますね!
■「間違えやすい」と「間違いやすい」
ところで、今回のタイトル、違和感がありませんでしたか?
「間違”い”やすいでは?」と思った方もいるかもしれませんね。
実は「間違”え”やすい」と「間違”い”やすい」はどちらも間違いではありません。これらはそれぞれ「間違える」「間違う」に形容詞がくっついた形です。「間違える」が他動詞で「間違う」が自動詞であるため、ニュアンスは若干異なりますが、どちらも正しい文法とされています。
■大切なのは「どう伝わるか」
ここまででご紹介したものなど、文法上の正誤がある表現は多いです。正式な文書など、フォーマルな場面では正しい表現をすることは大切ですが、一方で正しい表現をしなければ通じないわけではありません。
たとえば“ら抜き言葉”は、「見られる」だと複数の意味が混在してしまいますが、「見れる」と表現すると意味が明確になります。
また、熟語の誤読も、基本的には語の前後には言葉があり、その文脈から伝わる場面も多くあると思います。有名な誤読であれば、さらに意図が伝わりやすいはずです。例えば、「代替(だいたい)」を「代替(だいがえ)」と読んでしまうことがあるかと思いますが、これも語の前後からなんとなく意味は伝わるかと思います。他にも相殺(×そうさつ⇒○そうさい)や、先に述べました脆弱性(×きじゃくせい⇒○ぜいじゃくせい)なども、読み方が間違っていても、意味は伝わります。
言葉はただ単語の羅列ではなく、ニュアンスや意図を含むものです。もちろん、ビジネスの文書やフォーマルな場面では、丁寧で正確な表現を心がけることは大切です。ただし、日常のやり取りやカジュアルな場面では、柔軟に対応したいところです。間違いに敏感になりすぎず、「どう伝わるか」「どう受け取られるか」という視点を持つことが大事なのではないでしょうか。正しい日本語は勉強・吸収しつつ、TPOを踏まえ、より伝わりやすい表現をすることを心掛けたいですね。
ここまでご覧いただきありがとうございました。